ここ30年以上、日本の社会では女性の社会進出が進んだこともあり、専業主婦世帯数は減少し、共働き世帯は右肩上がりで増加しています。
以下は独立行政法人の労働政策研究・研修機構が発表している専業主婦世帯と共働き世帯の世帯数の推移を示したグラフです。
続きを読むここ30年以上、日本の社会では女性の社会進出が進んだこともあり、専業主婦世帯数は減少し、共働き世帯は右肩上がりで増加しています。
以下は独立行政法人の労働政策研究・研修機構が発表している専業主婦世帯と共働き世帯の世帯数の推移を示したグラフです。
続きを読むマイホームは土地を持っていても、その土地に勝手に家(建物)を好きなように建てられるわけではありません。
建築基準法という法律の定めに沿って適切なた手続きを行ったうえで建築する必要があります。
建築基準法以外にも、都市計画法や消防法など住宅建築に影響するさまざまな法律があります。建築基準法では、それらの法律と連携しつつ、家を建てるときに遵守しなければならないルールが明記されています。
基本的には、不動産会社や建築事務所・工務店は、家を建てるだけでなく、法に従って必要な手続きを進めてくれますので、詳細まで理解する必要はありませんが、私たち自身もある程度知識を持っておくことが大切です。
また、家を建てるときには多くの人が住宅ローンを利用することになりますが、住宅ローンの審査の中で、これらの手続きが適切に行われているかも確認されますので、これらのルールを守っていないと住宅ローンを借りることもできません。
この記事では、建築確認と住宅ローンの審査の関係について解説していきます。
続きを読む
国の統計調査によると、自営業、個人事業主、フリーランスと呼ばれる個人で事業を行なっている人はざっくり200万人ぐらいという統計データがあります。(サラリーマンや会社経営を行いながら個人事業主として働いている人も多く、「個人事業」だけで生計を立てている人の数の把握は非常に難しいと思いますが、総務省統計局が定期的に調査・発表しています。)
参考:https://www.stat.go.jp/info/today/pdf/197.pdf
個人事業者に雇用されている従業員もいますので、それらを含んだ場合、700万人程度が自営業や個人事業主や個人事業主に雇われる形の仕事をしていると言われています。
この記事では住宅ローンについて解説しています。
「個人事業主は住宅ローン審査に通りにくい」という話を聞いたことがあると思います。
実際、公務員や大企業の従業員と比較した場合には、住宅ローンに通りにくいというのは事実です。
中小企業庁の調査では、個人事業主の事業が10年後も存続している確率は数パーセントしかありません。個人事業主は大企業で働くよりも収入の安定性・継続性が不安定な働き方なのは事実ですし、住宅ローンを貸す側の金融機関からすると、厳しく審査せざるをえません。
実際に平均年収もサラリーマンより自営業・個人事業主が低いという統計結果が国税庁の調査で明らかになっています。
では、自営業・個人事業主の住宅ローン審査について解説していきたいと思います。
続きを読む
代表取締役やオーナー社長のような「会社経営者や起業家」と、一般的な企業や公務員として働くサラリーマンの明確な違いは「労働者か労働者ではないのか」と言う点です。
会社経営者は労働法で守られる労働者ではありません。
通常、会社の中では「オーナー」や「経営者」が大きな力を持っています。「社員」である「労働者」は会社の中では弱い立場です。
そのため、「経営者」が「労働者」を強い権力で不当に扱うことのないように「労働者」を守るため法令が用意されていたり、「労働者」を救う制度が用意されています。
「経営者」側を守る制度と言うものも多少存在しますが、事業や会社を運営しているリスクを補えるほどのものではありません。
この記事では、住宅ローンの審査で「社長、経営者、代表取締役、取締役などの会社経営者」がどのように評価されるのか、また、経営者からの住宅ローン申し込みがどのようなポイントを重視して審査されるのかについて解説しています。
続きを読む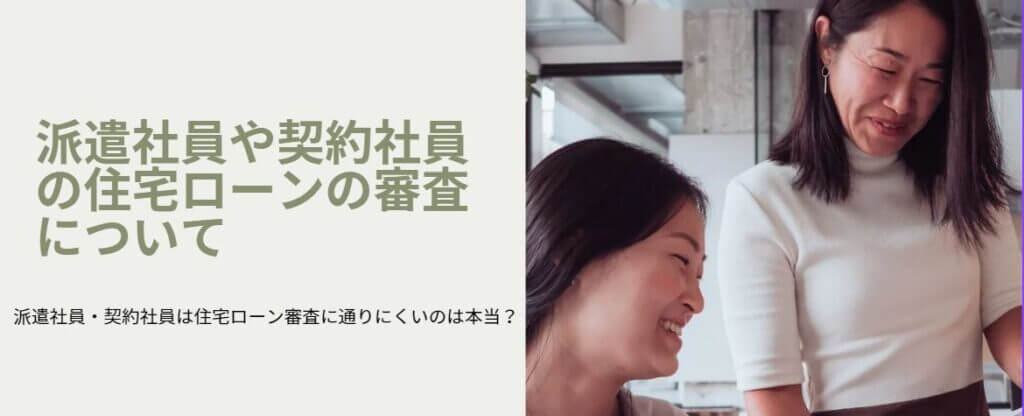
厚生労働省が実施している労働者統計によると派遣社員・契約社員として働く人は、日本国内に400万人以上存在しています。これは、日本の勤労者全体の7-8%程度を占めると言われていて、シェアはそれほど大きくありません。(総務省統計局・労働力調査はこちら)
この記事では派遣社員・契約社員として働く人の住宅ローンの審査について解説しています。派遣社員・契約社員は、いわゆる「非正規雇用」の社員で、日本では2000年以降に増加していて、近年は正規雇用との格差や同じ仕事をしているにも関わらず賃金が低いといった話題で注目を集めることが増えています。
正社員も終身雇用が当たり前の時代は終わりを迎えたとも言われています。能力や技術があれば正規雇用も非正規雇用が大差ないと考えることもできるのですが、今の日本の住宅ローンの審査においては「正規雇用」が有利で、非正規雇用(派遣社員など)がどうしても不利です。
この記事では、そんな非正規雇用(派遣社員・契約社員)の住宅ローン審査について解説しています。

小規模~中規模の法人が抱える課題の1つに経費精算コストがあります。正確に言うと、経費精算処理を行うための人件費が課題とされています。
例えば、原材料の仕入れ・従業員の出張や交通費の精算は、現金や銀行振込で処理するのが一般的ですが、大企業と異なり総務・庶務部門に十分なリソースを投下できない中小企業の場合、そもそも人手不足の問題もあります。
そのような手間を減らすために、社員に決済用・仕入用のカードを支給する方法があります。そうすることで、1件1件の経費精算の確認や登録・現金精算の手間を減らすことができます。
例えば、法人向けのクレジットカードやデビットカードなどです。
ところが、クレジットカードやデビットカードの場合、従業員の不正利用のリスクがあり、買い物はできますが、管理機能が充実しておらず、多数の従業員に配布することが困難です。
それらの課題を解決するのが「法人向けのプリペイドカード」です。プリペイドカードであれば、それぞれのカードにあらかじめチャージした範囲でしか利用できないので、不正利用のリスクを抑えることができますし、経費の予実の管理が行いやすいというメリットがあります。
続きを読むフラット35は国土交通省が所管する住宅金融支援機構が提供する長期固定金利タイプの住宅ローンです。

フラット35は、商品開発元である住宅金融支援機構に直接申し込むのではなく、住宅金融支援機構と提携する金融機関を経由して申し込む仕組みになっています。提携する金融機関はメガバンクや地方銀行・信用金庫・ネット銀行の他、住宅ローン専門のモーゲージバンクなど300社以上あります。
この記事ではフラット35の審査基準について解説しています。
フラット35と民間銀行が提供する住宅ローンの根本的な違いは商品を提供している法人の目的が全く異なると言う点です。
フラット35を提供する住宅金融支援機構は、独立行政法人で国土交通省などが所管しています。
独立行政法人である住宅金融支援機構は、幅広い国民の住環境の改善を支援することを目的としており、その為に提供されているのがフラット35です。一方、住宅ローンを提供している金融機関(銀行・信金・JAなど)は、あくまでも営利目的の法人です。
この違いが、フラット35が公的な役割をになっている住宅ローンと言われる理由です。
このように、フラット35は、「幅広い国民がマイホームを持てるようにすること」「優良・高性能な住宅を日本に普及させること」などの国が定める方向性・戦略に沿って提供されていると言う点を理解しておくようにしましょう。
その為、パート・アルバイトで働いている人でも利用できる可能性がありますし、団体信用生命保険に加入できない人でも利用できます。
住宅ローンの審査基準は、民間金融機関の住宅ローンとかなり異なっています。ダイレクトに言ってしまえば、フラット35は一般的な住宅ローンよりも審査に通りやすい住宅ローン、つまり、審査基準が甘い面がある住宅ローンです。
続きを読むSBIアルヒは2010年度から連続してフラット35の取り扱いシェアで1位を獲得し続けているフラット35最大手の住宅ローン専門の金融機関です。
SBIアルヒでは豊富な商品が提供されていますが、SBIアルヒで人気を集める主力商品にARUHIスーパーフラットという商品があります。
この商品は、一定の頭金を用意することで一般的なフラット35よりも低い金利で借り入れできたり、ワイド団信を利用できるなどの特徴があります。
続きを読む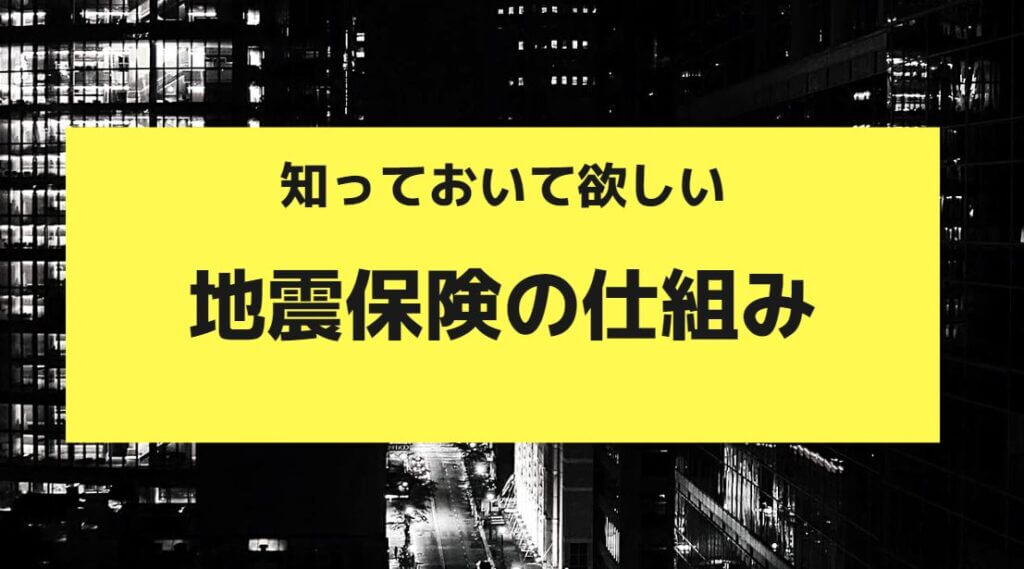
近年、大規模な地震が多く発生しています。2024年1月の能登半島地震は記憶に新しいですが、その後も、震度4を超える程度の地震が日本各地で多く発生しています。
この記事ではマイホームの地震被害に備えるための保険である地震保険について解説したいと思います。「国による再保険」という仕組みは理解しておいた方が良いので少し掘り下げて解説したいと思います。
続きを読む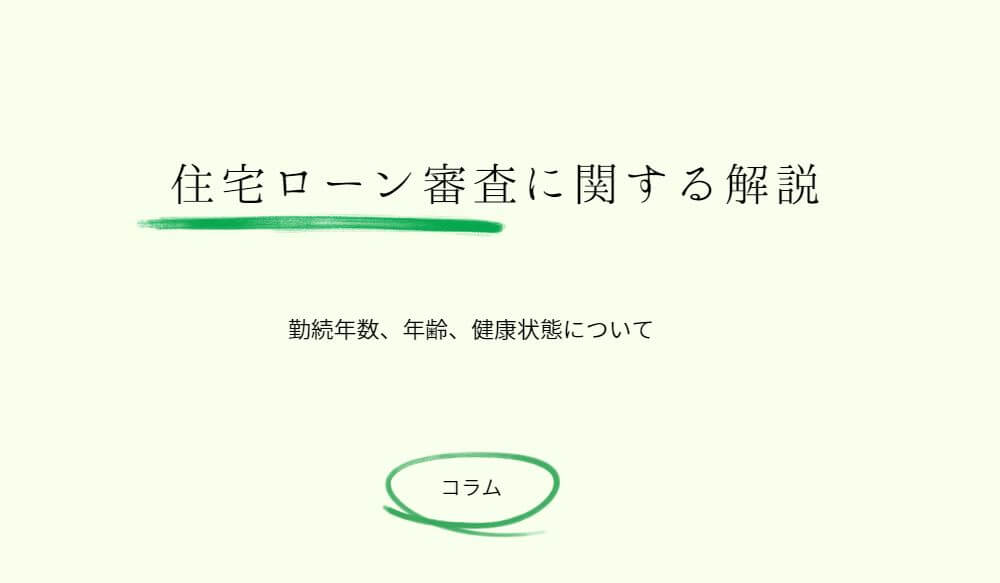
住宅ローンは、個人が借りるローン商品の中でも特に厳格に審査されます。
カードローンなどの審査と比べて住宅ローンの審査は複雑です。住宅ローンは、数千万・数億円単位のお金を貸して、10年以上かけて返済されるため、金融機関としては、様々な観点で総合的に審査する必要があるためです。また、それらの審査基準も金融機関により大きくことなります。
この記事では住宅ローンの審査で必ず確認される「勤続年数」「年齢」「健康状態」について解説したいと思います。なお、「健康状態」は銀行ではなく保険会社が提供する団信の加入審査という形で審査されます。
マイホームは人生最大の買い物です。マイホームを買うために借りる住宅ローンは人生最大の借金です。
有利な住宅ローンを利用するためには、審査される点を把握しておくことが大切です。
住宅ローンの全ての審査基準を公表している金融機関はありまえん。
また、住宅ローンの審査で落とした人大して、なぜその人が審査に落ちたのかその理由を丁寧に教えてくれる金融機関もありません。住宅ローンの審査にはAIが活用されるようになって複雑化していて、金融機関側も簡単に教えることができません。
ただし、「勤続年数」「年齢」「健康状態」は比較的わかりやすい審査項目です。なぜなら、審査基準が明示されているケースが多い審査項目だからです。
それでは、主要な住宅ローンの審査で「勤続年数」、「年齢」、「健康状態」がどのように扱われているのか、順を追って確認していきましょう。
続きを読む