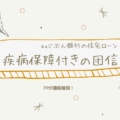2007年9月に住宅ローンの取り扱いを開始した住信SBIネット銀行は、累計の融資実行額が10兆円を突破し、今もハイペースで住宅ローン利用者を増やし続けている銀行の1つです。

住信SBIネット銀行では、公式サイトから申し込む住宅ローン(WEB申込コース)やSBIマネープラザなどの店舗から申し込む住宅ローン(対面相談コース)など、いくつかの住宅ローンを提供しています。
住信SBIネット銀行の住宅ローンは第三者の調査や外部の評価機関などによる評価も高く、例えば、2014年に発表された日本能率協会総合研究所(東京都港区)による「住宅関連企業従事者に聞いた『住宅ローン』に関する調査」のうち「住宅ローン商品の評価」において、全項目で1位の評価を得たり、カカクコムやオリコンのランキングでも常に上位にランクインしています。
これは、一般の人からの高い評価はもちろん、住宅関連で働く住宅のプロ が住信SBIネット銀行の住宅ローンを高く評価していることを意味しています。
この記事では、そんな住信SBIネット銀行の住宅ローンに落とし穴が無いのか、また、気を付けなければならないポイントと対策をまとめています。世の中に完璧な住宅ローンというものありませんので、しっかりと理解・対策をして住信SBIネット銀行の住宅ローンを申し込むようにしましょう。
- 当初期間金利引下タイプの固定期間終了後の金利水準に注意
- 審査に時間がかかることがある
- 年収基準など審査基準が明確になっていない
- 無料でセットされる”全疾病保障”が活躍するケースは少ない
- 審査の結果で金利が高くなる可能性がある
目次
住信SBIネット銀行 住宅ローンの落とし穴
審査結果により金利が上乗せされる
住信SBIネット銀行の住宅ローンは、審査の結果で金利が上乗せされる可能性があります。
住信SBIネット銀行に限らず、一般的な銀行の住宅ローンでも採用されている仕組みで、審査の中で融資金利が決定されますので、審査に通った場合でも、必ずしも「最も低い金利」で住宅ローンを借りられるとは限らないという点には注意しておくようにしましょう。
住宅ローン審査に時間がかかる場合がある
住信SBIネット銀行の住宅ローン審査期間や融資実行までかかる時間は早いほうではありません。特にネット銀行には、全国各地から申込が集中します。人気がある住宅ローンであれば、次々と申込があり、審査手続きを進めていく必要があります。
また、繁忙期は普段以上に審査に時間がかかることもあるので、余裕をもって申し込むようにしましょう。
住宅ローン審査基準があいまいな点も
住宅ローンの中には、勤続年数、年収、職業などの条件が商品説明書に明示されていることが多くあります。
たとえば、住宅ローン審査基準に厳しいソニー銀行であれば、派遣社員・契約社員の利用が不可であることを明記しています。一方で、住信SBIネット銀行では勤続年数、年収、職業などの審査条件が明示されていません。
総合評価で審査結果を決めているので明確に開示できないものと推測できますが、利用者側の視点からは住宅ローン審査を申し込む際の不安材料と言ってよいでしょう。
当初固定期間経過後に注意
住信SBIネット銀行に限らず、メガバンク、地銀などでも取り扱っている当初固定期間設定型の住宅ローンについては期間が終了したタイミングで大幅に金利が上昇することに注意が必要です。
特に「当初期間引下げプラン」の場合、当初期間の金利を低くする代わりに終了後の金利が高くなるプランなのでしっかりと確認しておくようにしましょう。
ワイド団信の取り扱いがない
住宅ローンを組む際に加入が必須となるのが団体信用生命保険(団信)です。
団信は住宅ローン契約者(債務者)が死亡したり、所定の高度障害を負った場合に保険金が支払われ住宅ローン残高がゼロになる生命保険であり、生命保険であるために加入時に健康状態に関する告知をする必要があります。
具体的には過去の病歴や通院歴を告知し、保険会社で加入か審査を行います。この審査に落ちると住宅ローン審査に落ちることます。
ライバルと言えるネット銀行のauじぶん銀行やソニー銀行では、一般的な団信に加入できない人のために、加入条件を緩和したワイド団信を扱っていますが、住信SBIネット銀行では扱っていません。
一般団信に加入できない方は残念ながら住信SBIネット銀行で住宅ローンを組めないこととなります。
こうした方は前述のauじぶん銀行のワイド団信に申し込みをするか、団信の加入が必須ではない、住信SBIネット銀行のフラット35への申し込みを検討するのがよいでしょう。
店舗でも相談・申し込みが可能
住信SBIネット銀行は、WEB申込コースのほかに、SBIマネープラザなどの店舗で申し込める住宅ローン(対面)という商品も提供しています。
例えば、以下のSBIマネープラザの店舗などで相談することができます。
- 大宮住宅ローンプラザ
- 新宿中央支店
- 秋葉原支店
- 横浜住宅ローンプラザ
- 名古屋支店
- 大阪支店
- 神戸住宅ローンプラザ
- 福岡中央支店
全疾病保障の適用条件
住信SBIネット銀行の住宅ローンの人気の理由に無料で付帯される全疾病保障があります。この全疾病保障は病気やケガなどすべてを保障するものであり幅広い保障が受けれることメリットです。
しかし、気を付けておきたい落とし穴に、この全疾病保障の保険金受取の条件があります。
この住信SBIネット銀行の全疾病保障は、病気やケガで働けない状態が1年経過しないと対象になりません。また、8疾病以外の病気や怪我では入院をしていることが条件です。病気や怪我で1年働けない、入院している状態になるのはかなりレアケースと考えられます。
全疾病が全ての病気や怪我を保障してくれる一方で、1年以上の入院や就業不能を条件としているなど実際にその保障を受けるハードルはかなり高い点は落とし穴になりますので注意が必要です。
平均的な入院日数は?

厚生労働省が発表している患者調査によると35歳から64歳の病気や怪我による平均入院日数は21.9日です。平均値を見る限り、全疾病保障を受ける状態になるのは極めて稀であることが読み取れます。