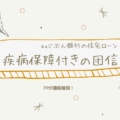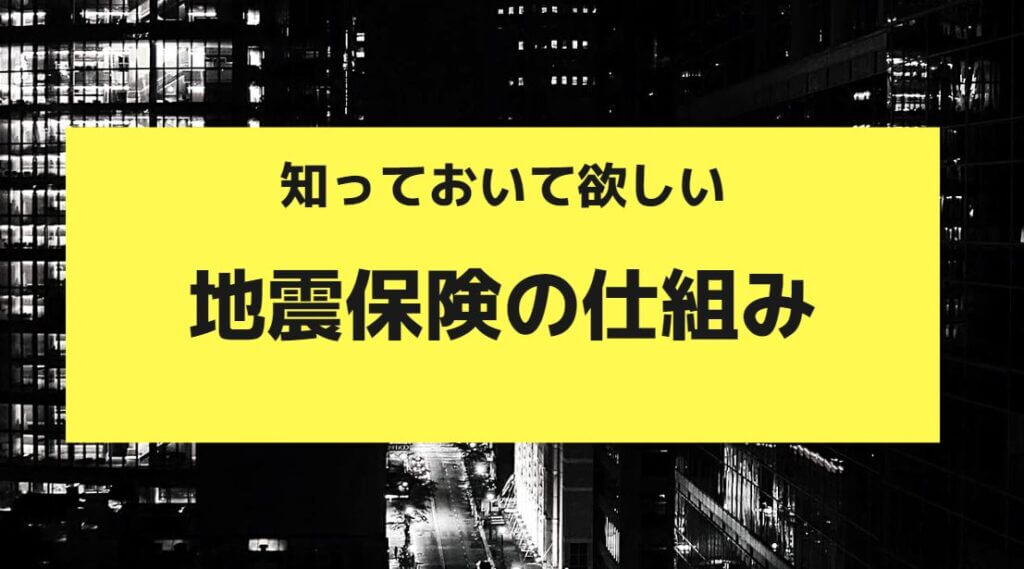
近年、大規模な地震が多く発生しています。2024年1月の能登半島地震は記憶に新しいですが、その後も、震度4を超える程度の地震が日本各地で多く発生しています。
この記事ではマイホームの地震被害に備えるための保険である地震保険について解説したいと思います。「国による再保険」という仕組みは理解しておいた方が良いので少し掘り下げて解説したいと思います。
大規模地震発生時の地震保険金支払額
最初に、近年発生した大規模地震で損害保険会社が支払った地震保険の支払総額を確認しておきましょう。東日本大震災が圧倒的なのは言うまでもありません。
能登半島地震は744億円(日本損保協会・2024年4月22日発表)で、史上7番目の保険金の支払額です。保険金支払額からも被害の大きさがわかります。
東日本大震災:1兆2,167億円
平成28年熊本大地震:3,621億円
阪神・淡路大震災:783億円
能登半島地震:744億円
上記の金額は地震による被害の規模を計る指標にもなりますが、地震保険に加入していたことで生活再建のためのお金を受け取ることができた保険に加入していたことの意義を計る指標でもあります。
地震保険の勘違い
実は、「大規模地震が起こった場合、その被害は保険会社が保険金を支払うことができる規模ではないので地震保険に加入していてもほとんど意味がない」と考えている人が一定数います。
その認識は正しくありません。もちろん、大規模地震対する備え・保険は1つの保険会社だけで対応できるようなものではありません。
仮に東日本大震災の規模の地震が首都圏直下で発生した場合、東日本大震災の数倍から数十倍の規模の被害が発生すると言われています。南海トラフ大地震の最大損害額も同様です。
実際、民間企業である保険会社がいつ起こるか予想できない地震のために1兆円を超える単位のお金を用意することはできません。
したがって、「大規模地震が起こった時に保険会社が保険金を支払うことができる規模ではない」という点は正解です。
国による再保険の仕組み
実は、地震保険は保険会社の責任負担を決めて、それを超える部分を保険会社に対して国が支払う仕組み(日本政府による再保険)で成り立っています。
地震大国である日本では国全体で大規模地震に備える仕組みになっているのです。直接、国が保険を提供することは難しいため、保険会社を国がサポートすることで民間企業の力だけでは提供できない地震保険という仕組みが成りたっています。
ちなみに、1回の地震で国が支払う保険金の金額は国会での承認が必要で、現時点で、約11兆円6,000億円と定められています。
民間企業が支払う保険金と合わせて12兆円です。単純計算ですが、東日本大震災9回分が予算化されていることになりますので、後半部分の「加入していてもほとんど意味がない」は勘違いであることがわかると思います。
なお、東京都直下型で東日本大震災級の地震が起きると11兆円程度では足りないと試算されています。
財務省もこの事実は認識していて、万が一、11兆円で足りない規模の被害がでた場合は、特別予算を確保する動きをとることで事前に示し合されていますので、この11兆円が上限というわけではありません。
地方エリアの大地震の場合、この予算を超える可能性はほとんどありませし、安心して地震保険に加入して欲しいと思います。
地震保険における保険会社は窓口会社に近い
地震発生時に支払われる最大額の地震保険金のうち97%が政府で民間の保険会社はわずか3%しか負担しておらず、実は地震保険は日本政府が提供している保険だということがわかります。
実は、私たちが地震保険を契約しても保険会社にはほとんど儲けがありません。
保険会社から保険の勧誘やダイレクトメールなどで商品の案内を受けたことは誰しもがあると思いますが、地震保険への加入を積極的に案内されたことはあるでしょうか?ほとんどないと思います。
地震保険はその性質上と制度の仕組み上、保険会社にとってビジネスとして成り立っていないからです。
地震保険は家を建て替えるために入る保険ではない
地震保険に加入していたとしても新しくマイホームを建て直せるほどの保険金が受け取れるわけではありません。このせいで地震保険になんか加入しても意味がないと勘違いしてしまう人が増えてしまっているのだと思いますが、マイホームが全壊しても住宅ローンは残ります。今までと同じように返済を続けなければならないのです。
存在しない家のためのローンを支払い続けるのは非常につらいものです。そんなときに、住宅の3割~5割の保険金を受け取れる地震保険に加入しているかどうかは大きな分岐点になりかねません。
地震保険は黙っていても保険会社から勧誘されることもほとんどありませんので加入せずに終わってしまいがちです。
相次ぐ自然災害を教訓に地震保険への加入を今一度検討してみるようにしてください。